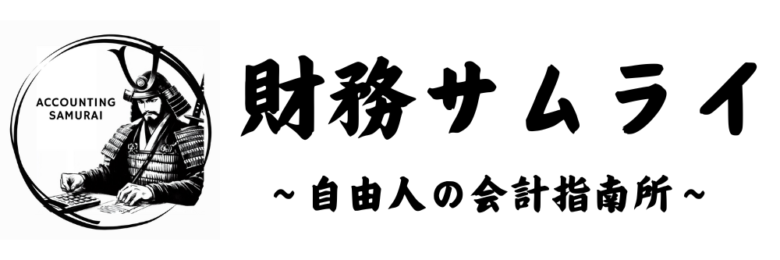- 税理士に依頼するとどんなメリットがある?
- 税理士に頼む方法やタイミングが知りたい!
- 実際に受けられるサービスの内容が知りたい!
このような疑問や要望に応えます。
税理士に依頼すると、さまざまなメリットやデメリットがあります。
経営者やフリーランスにとっては、税務や会計の作業の負担を軽減し、本業に集中するためのサポートとなります。
しかし、依頼にはコストが伴い、場合によってはデメリットも存在します。
この記事では、税理士に依頼するメリットとデメリットを具体的に解説し、依頼方法や適切なタイミングについても詳しく説明します。
さらに、税理士の主な業務内容や報酬についても触れ、どのようにして最適な税理士を見つけるかのポイントも紹介します。
税理士の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
税理士の基本知識

税理士とは?
税理士とは、税金や会計の専門家です。
税務申告や財務管理、経営サポートなど幅広い業務を担当し、法律に基づいた正確なアドバイスを提供します。
税理士を利用することで、税務リスクの軽減や業務の効率化が期待できます。
税務リスクとは
税務リスクとは、税務申告のミスや税法の違反、適切な税務処理ができていないことによるペナルティや罰金などをいいます。税務リスクを適切に管理しないと、追徴課税や税務調査、延滞税や加算税などの問題が発生する可能性があります。
税理士の業務内容
税務申告の代行
税理士は税務の専門知識を活用し、決算や確定申告の代行をします。
これにより、納税者は税務の煩雑さから解放され、本業に集中することができます。
財務・会計のアドバイス
税理士は企業や個人の財務状況を分析し、財務管理の改善策を提案します。
正確な財務情報は経営判断に不可欠であり、税理士のアドバイスにより経営の健全性を保つことができます。
資金調達と融資のサポート
税理士は金融機関との交渉や、融資を受ける際に必要な試算表の作成をします。
有利な条件での資金調達を実現し、企業の財務基盤を強化します。
経営コンサルティング
税理士は経営戦略の立案や財務計画の策定をサポートします。
経営者のビジョンを実現するための具体的なプランを提供し、事業の成長を促進します。
税理ダメなのか、コンタクトをとる前に知っておきたいですよね。
具体的な税務内容
具体的な税務内容
- 領収書や請求書などをもとに会計処理
- 決算書類、確定申告書等の作成、申告代行
- 売上や利益などの損益状況を顧問先へ説明
- 経営相談
- 年末調整の計算
- 税務調査の立ち会い
このように税理士が行っている仕事は決算や確定申告を中心に、経営相談も含め幅広い内容となっています。
以下のものは税理士の専門外なので、ほかの専門家に相談しましょう。
- 社会保険料や雇用保険料
- 生命保険
- 補助金関係
くわしい税理士もいますが、やはり専門外ですので、答えられる範囲は限られてきます。
社会保険料については「社労士」、生命保険は「保険会社」、補助金関係は「主催」に確認しましょう。
税理士に依頼するメリット&デメリット
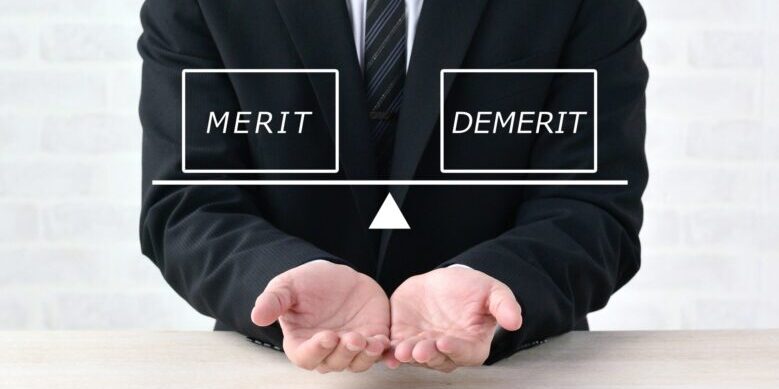
税理士に依頼する4つのメリット
- 適切な会計処理、税務処理
- 税制改正の情報や節税のアドバイス
- 税務調査の対応
- 資金調達や補助金申請のサポート
4つのメリットについてそれぞれ解説します。
適切な会計処理、税務処理
税理士に依頼することで、法律に基づいた適切な会計処理、税務処理をすることができます。
税理士は会計や税金の専門家です。
適切な勘定科目の判断や会計処理が行われ、税務リスクの軽減にもつながります。
税理士は最新の税法に精通しており、法律に基づいた正確な申告を行うことが可能です。
税制改正の情報や節税のアドバイス
税制改正の情報や対策、節税のアドバイスが受けられるのも大きなメリットです。
税法は頻繁に改正されるため、最新の情報を把握することは非常に重要です。
近年ではインボイス制度や電子帳簿保存法が施行されています。
税理士は、青色申告の特典を利用した節税や小規模企業共済などの基本的な節税のほか、適切な節税対策を提案してくれます。
税理士は、財務状況やビジネスの特性に応じた最適な節税対策を提案し、法的に適正な方法で税負担を最小限に抑えるサポートをしてくれます。
>>>【これを知らなきゃ損!】フリーランスが知っておくべき節税の基本!
税務調査の対応
税務調査では、間違った申告や記録の不備により追徴課税のリスクが生じます。
税法に違反する場合や税金を適正に支払っていない場合、所得の再計算が行われ、追徴金を支払う必要がでてきます。この追徴課税には延滞税や加算税といった罰金が課される可能性があります。
たとえば、収入を隠して申告しなかったり、経費を不正に計上したりすると、不納付加算税や重加算税といった高税率の税金が課されるリスクがあります。
税理士のサポートを受けることで、リスクを把握し、事前に対処することが可能です。
税理士による税務調査の対応には、以下のようなメリットがあります。
専門的な知識と経験
税理士は税務の専門家であり、税務調査に関する豊富な知識と経験を持っています。
税務調査の際には、税法や手続きに詳しい税理士が立ち会うことで、スムーズに調査を進めることができます。
誤解やミスの防止
税務調査では、専門用語が多く使われるため調査官とのやり取りで誤解やミスが生じることがあります。
税理士が同席することで、税務の専門用語や手続きについて正確に説明し、誤解を防ぐことができます。
これにより、調査の結果に不利な影響を与えないようにすることができます。
精神的な安心感
税務調査は、多くの経営者にとって大きなストレスとなります。
税理士が立ち会うことで、専門家のサポートを受けられるため、精神的な安心感が得られます。
税理士は、調査中の対応方法や準備すべき書類についてもアドバイスを提供し、調査に対する不安を軽減します。
適切な対応策の提案
税理士は、調査の結果に基づいて適切な対応策を提案してくれます。
例えば、指摘された問題点に対する修正申告や改善策の提案を行い、将来的な税務リスクを軽減するためのアドバイスを提供します。
時間と労力の節約
税務調査に対応するためには、多くの時間と労力が必要です。
税理士がサポートすることで、経営者は本業に集中することができ、調査対応にかかる時間と労力を節約することができます。
税理士のサポートを受けることで、税務調査において適切かつ迅速な対応が可能となり、経営者の負担を大幅に軽減することができます。
また、調査官にとっても税理士は大きな存在であり、税務調査の場に税理士がいるかいないかで対応も違ってくるでしょう。
>>>【税務調査対策】調査されやすいポイント&申告漏れを指摘されないための会計処理のポイント解説!
資金調達のサポート
資金調達の際、税理士からサポートを受けられます。
税理士による資金調達のサポートには、以下のようなメリットがあります。
専門的な知識と経験
税理士は資金調達に関する豊富な経験を持っています。
これにより、適切な書類の作成や手続きの進め方について、的確なアドバイスを提供してくれます。
成功率に影響
税理士は、金融機関との交渉経験が豊富です。
また、税理士の作成した決算書や試算表は、金融機関の信頼性が上がり、資金調達の成功率を高めることができます。
税理士のサポートを受けることで、資金調達や補助金申請がスムーズに進み、企業の財務基盤が強化されます。
税理士に依頼する3つのデメリット
- 顧問料や決算料などの手数料がかかる
- コミュニケーションの手間と時間
- 丸投げの場合、月次の資料が出るのが遅い
3つのデメリットについてそれぞれ解説していきます。
顧問料や決算料などの手数料がかかる
税理士に依頼すると顧問料や決算料、確定申告料などが発生します。
税理士を利用する際には、顧問料が発生します。
顧問料は税理士の経験や業務内容によって異なり、その相場を理解することが重要です。
そして、顧問料のコストパフォーマンスを評価し、その費用がビジネスにとって有益であるかを判断する必要があります。
また、調査立会などの臨時業務は別途料金がかかる場合があります。
コミュニケーションの手間と時間
税理士との打ち合わせや定期的な報告が必要です。
打ち合わせでは、税理士の専門分野やサービス内容を確認し、今後のコミュニケーションの基盤を築くことが求められます。
業績の説明などの定期的な報告とコミュニケーションを通じて、最新の状況を把握し、適切なアドバイスを受けることができます。
また、一定期日まで通帳や領収書、請求書やクレジットカード明細などの会計に関する資料を準備する必要があります。
資料を渡すのが遅れると、会計や決算の処理も遅れるので、前もって準備しておくことが必要です。
丸投げの場合、月次の資料が出るのが遅い
領収書の整理や帳簿の作成を丸投げしている場合、月次の試算表が出るのが遅くなります。
理由は、税理士側での作業量が増えるためです。
領収書などを整理してから、会計ソフトに入力する必要があります。
試算表の作成までは、領収証や請求書などを渡してから早くて2週間ほど要します。
試算表作成までのイメージ
- 1月分の資料を2月前半に渡す
- 領収証の整理や会計ソフトの入力で2週間かかる
- また、不足資料や確認が必要なものがあればさらにかかる
- 早くても1月の試算表を受け取るのは2月後半
業績を確認できるのは1か月後になるケースがほとんどです。
もし、業績を早くつかんでおきたい場合は、自社で会計ソフトに入力することで可能となります。
自社で会計ソフトに入力していれば、リアルタイムで業績を把握することができます。
税理士の費用と費用対効果
税理士費用の相場
ポイント
確定申告の依頼費用は業務内容により異なります。
領収書や請求書のデータを会計ソフトに入力する記帳業務の依頼費用は月3万円程度が一般的です。
また、確定申告のみの依頼であれば10~20万円前後が相場です。
ただし、売上規模や取引量などによって費用は増減するため、売上規模が大きいと費用が増え、取引量が少ないと費用が減額される場合があります。
経理担当者を雇う場合との比較
経理担当者を雇う場合、給与のほか社会保険料や雇用保険料などの追加コストが発生し、固定費が増加する可能性があります。
税理士と経理担当者の費用対効果を比較することが重要です。
税理士の顧問料は、経理担当者の雇用コストよりも低い場合が多く、費用対効果に優れています。
コストパフォーマンスの見極め方
依頼内容と費用のバランスを考慮する必要があります。
税理士に依頼する業務内容を明確にし、その内容に見合った費用を支払うことで、コストパフォーマンスを最適化できます。
また、長期的な経済効果を評価することも重要です。
税理士のサポートにより実現した節税効果や業務効率化の具体例を挙げ、長期的な経済効果を評価します。
税理士に依頼する方法

税理士を探す手段
- 「税理士に依頼するといっても接点がない」
- 「敷居が高く感じて、どうやってコンタクトをとるべきかわからない」
こんな風に思われている方も多いかと思います。
他の事業者の方はどういうルートで税理士に依頼しているのか気になりますよね。
実際に体験したことも踏まえて税理士へコンタクトをとる方法をご紹介します。
- 知り合いから紹介を受ける
- 所属している業者団体や取引がある金融機関からの紹介
- 税理士紹介サービスを利用する
それぞれの方法について解説していきます。
知り合いから紹介を受ける
友人やビジネスパートナーなど、知り合いから税理士を紹介してもらう方法です。
信頼できる人からの紹介なので、安心して依頼できることが多いです。
また、紹介者との信頼関係があるため、税理士も丁寧に対応してくれることが期待できます。
所属している業者団体や取引がある金融機関からの紹介
商工会やロータリークラブなどの業者団体や、取引のある金融機関から紹介してもらう方法です。
業界団体や金融機関のほとんどは、税理士と取引があるため、実績のある税理士を紹介してもらえる可能性があります。
特に、業界の特性や金融機関のニーズに詳しい税理士を紹介してもらえることが期待できます。
税理士紹介サービス
インターネット上の税理士紹介サービスを利用して、自分の条件に合った税理士を見つける方法です。
多くの選択肢から自分に合った税理士を見つけることができます。
オンラインで簡単に検索でき、税理士のプロフィールや口コミを確認できるため、比較検討しやすいです。
税理士ドットコムのような税理士紹介サービスを利用するものよいでしょう。
>>>税理士ドットコムの料金・手数料やサービス内容を徹底解説!|安心して利用するための完全ガイド
税理士を選ぶポイントと注意点
専門分野の確認
業界特化型税理士の選び方を考えます。
自分のビジネス分野に特化した税理士を選ぶことで、より専門的なアドバイスを受けることができます。
例えば、IT業界や飲食業界など、特定の業界に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
税務分野の専門性も確認することが重要です。
税理士の専門分野が自分のニーズに合致しているかを確認することで、効果的なサポートを受けることができます。
税理士の経歴と実績の確認
税理士の資格と経験年数を確認することが重要です。
税理士の資格や経験年数を確認し、その実績を評価することで、信頼性の高い税理士を選ぶことができます。
また、税理士の口コミや評価をチェックすることも重要です。
他の顧客の口コミや評価を参考にすることで、税理士のサービス内容や信頼性を確認することができます。
コミュニケーションの取りやすさ
税理士との面談の頻度と対応方法を確認することが重要です。
定期的な面談を通じて、税理士と密にコミュニケーションを取ることが大切です。
これにより、最新の情報が聞けたり、適切なアドバイスを受けることができます。
また、オンライン面談の活用も重要です。オンライン面談に対応している税理士を選ぶことで、移動時間を節約し、効率的にコミュニケーションを取ることができます。
また、税理士との付き合いは長くなることが多いので、年齢や性格により、コミュニケーションをとりやすいかどうか、といったところも重要視すべきです。
税理士との付き合い方

「税理士の先生とどう接したらいい?」
「格式が高い感じがしてどう付き合えばいいかわからない」
こんな不安をお持ちの方は多いと思います。
税理士は先生と呼ばれる職種ではありますが、言ってみれば、普通のビジネスマンだったり、サラリーマンだったりします。
特にかしこまることなく、普通のビジネスマナーをもって接すれば大丈夫です。
とはいえ、弁護士などと同様に特異な業種だとは思いますので、業務委託する際の付き合い方やビジネスパートナーとしての付き合い方についてまとめましたので、今後のご参考にしていただけたらと思います。
税理士はビジネスパートナー
税理士は会計や税金分野におけるビジネスパートナーです。
税務や会計のエキスパートである税理士は、税務知識によりクライアントの節税を図ったり、帳簿や帳票の作成で経営をサポートします。
煩雑な会計処理を任せることで本業に専念することができ、節税提案やアドバイスを受けることで財務状況の健全化につながります。
ですから、税理士は税務や会計の分野でビジネスをサポートするパートナー的な存在といえます。
会計を依頼する上での付き合い方
- 期日までに会計資料を準備する
- 信頼して会計関係の情報はすべて渡す
- 確定申告や決算時期は協力的に
- 会計や経営的な質問は全然しても大丈夫
それぞれの内容について解説します。
期日までに会計資料を準備する
領収書や請求書などの会計資料を期日までに準備して渡すようにしましょう。
資料を渡すのが遅れると、税理士側での処理も遅れ、自社の経営状況を把握するのが遅くなります。
また、領収書などの内容について質問を受けることがありますが、疑っているわけではなく、適正な会計処理をする上での質問ですので、居力的に回答しましょう。
信頼して会計関係の情報はすべて渡す
会計に関する情報はすべて渡すようにしましょう。
「この通帳は見られたくない」「この補助金は事業と関係ないからいらないだろう」という場合もあるかと思いますが、税理士との信頼関係は大事ですので、包み隠さず情報を渡しましょう。
万が一、隠し事をしたことにより脱税につながってしまったり、脱税まで行かなくても税務署から指摘を受けてしまうと、決算書や確定申告書については税理士が代行して作成しているため、税理士の評判や信用にも大きな影響がでます。
そういった場合、信頼関係が崩れ、顧問契約解除となってしまうことも十分に考えられます。
確定申告や決算時期は協力的に
確定申告や決算時期は、税理士にとって繁忙期となります。
申告に関する多くの処理をする時期ですので、内容の確認や不足資料の催促があった場合には協力的に対応しましょう。
対応が遅れてしまうと、申告自体に影響がでてしまうことも考えられます。
会計や経営的な質問は全然しても大丈夫
会計に関して不明な点や経営的な質問は全然しても大丈夫です。
むしろ質問していたほうが「この人はこういうところが気になっているんだ」と税理士側でも把握できるので、求める情報を提供してもらえるかもしれません。
ちなみにですが、意外に質問が多かったのが、社会保険料や生命保険についてですが、税理士は社会保険料や保険などに関しては専門外ですので、社労士や保険会社などの各専門家に質問するようにしましょう。
税理士もビジネスをしている
税理士も言ってみればビジネスマンですので、普通にビジネスとして接してオッケーです。
数十年前は「先生」と呼ばれ尊い扱いをされていた頃もあったと聞きますが、今はそんなことはありません。
税務会計の専門家としてビジネスのパートナー的な位置づけになっているところがほとんどです。
特にへりくだらなくても全然大丈夫ですし、心づけなどに気を使わなくても大丈夫です。
自分で確定申告を行うべきか?税理士に依頼するべきか?

自分で確定申告すべきか、税理士に依頼するべきか、またはいつのタイミングで税理士にお願いしたらいいのか、気になるところですよね。
自分で確定申告を行うメリットとデメリット
自分で確定申告を行うメリット
自分で確定申告を行う場合、コストを削減できる点が最大のメリットです。
税理士に依頼する場合の顧問料が発生しないため、節約が可能です。
また、自分で申告を行うことで税務に関する知識を深めることができ、ビジネスの金銭感覚を養う機会となります。
自分で確定申告を行うデメリット
一方で、自分で確定申告を行う場合のデメリットとして、時間と労力がかかる点が挙げられます。
税務知識が不十分だと、申告ミスや法的リスクが生じる可能性が高まります。
特に、複雑な税務処理には専門知識が必要であり、間違った申告は追徴課税やペナルティのリスクを伴います。
税理士に依頼するおすすめのタイミング
- 消費税の課税事業者になったとき
- 本業が忙しくなって会計ができないとき
- 会計の方法がわからないとき
- 法人成りした場合
それぞれのタイミングについて解説します。
消費税の課税事業者になったとき
消費税を納める課税事業者になったタイミングで税理士に依頼するのがおすすめです。
消費税の会計処理は、8%と10%の複合税率の処理にくわえ、インボイス関連の処理があるので、判断も含め難しくなってきています。
レシートや領収書、請求書の記載内容から取引ごとに判断して、会計処理をする必要がありますので一般の方は大変な困難を感じるでしょう。
消費税の課税事業者になったら、税理士への依頼を検討してみましょう。
本業が忙しくなって会計に手が回らないとき
本業が忙しく、会計処理に手が回らないときは税理士依頼を検討しましょう。
本業が忙しいということは、売上規模が大きくなり、利益状況もよく納税額も大きくなることが予想されます。
税理士は税金の専門家ですから、節税の提案が受けられます。
また、規模が大きくなり納税額も大きくなってくると税務調査の可能性を考えて、調査対策といった面から税理士に依頼して適切に会計処理してもらっていたほうが安心を得られるかもしれません。
会計の方法がわからないとき
会計がわからない方は税理士に会計処理を依頼しましょう。
領収書や請求書などの会計資料を預けると、試算表や決算書を作成してもらえるフルサポート対応の税理士さんもたくさんいらっしゃいます。
会計がわからない場合は、税理士に依頼するのが一番おすすめです。
法人成りした場合
法人の決算・申告処理は、個人事業主の確定申告より、複雑でより専門知識が必要です。法人成りしたら税理士に会計処理を依頼しましょう。
個人事業主と法人の違い
個人事業主の税務
個人事業主の税務は、法人と比べるとシンプルです。
個人事業主は自分で申告を行うことが一般的ですが、必要に応じて税理士のサポートを受けることも有効です。
法人の税務と必要性
法人の税務は複雑であり、専門知識が求められます。
法人税や消費税の申告、さらに経理システムの整備など、多岐にわたる業務を効率的に行うためには、税理士のサポートが不可欠です。
ケーススタディ
税理士に依頼して成功した事例
事例1:新規事業の成功
- 新規事業を立ち上げる際、税理士に相談することで、適切な事業計画の立案や資金調達のサポートを受けることができた。
- 店舗兼住宅を建てる時も、住宅ローン控除の要件を聞いていたので無事に制度を利用できた。
事例2:資金調達の成功
- 税理士のサポートを受けて融資申請を行い、無事に資金調達を成功させることができた。
- 適切な書類作成と金融機関との交渉を通じて、有利な条件で資金を確保することができた。
自分で確定申告を行って問題が発生した事例
事例1:税務調査でのトラブル
- 自分で確定申告を行った結果、税務調査で申告ミスが発覚し、追加の税金とペナルティが課せられる結果となった。
事例2:余計な税金を払うことに
- 節税の知識がなかったために、余計に税金を払う結果となってしまった。
- 税理士に依頼していれば、事前にアドバイスや情報が聞けていたかもしれない。
税理士選びに失敗した事例とその教訓
事例1:コミュニケーション不足
- コミュニケーションがうまく取れず、適切なサポートを受けることができなかった。
- 定期的な報告やミーティングが不十分であり、経営判断に必要な情報が得られなかった。
事例2:専門性の不足
- 選んだ税理士が自分の業界に詳しくなく、専門的なアドバイスが得られなかったため、売上増対策ができなかった。
- 業界特化型の税理士を選ぶことの重要性を学んだ。
税理士に依頼する4つのメリットと3つのデメリット徹底解説:まとめ

税理士に依頼するメリットとデメリットについての解説を通じて、税理士がどのようにビジネスのサポートをするかをご理解いただけたと思います。
税務の専門知識を持つ税理士は、適切な会計処理や節税対策、税務調査対応など多岐にわたるサポートを提供しますが、一方でコストやコミュニケーションの手間などのデメリットも存在します。
最適な税理士を見つけるには、知人の紹介や業者団体、インターネットの紹介サービスを活用することが効果的です。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
執筆者:プレノト
会計事務所時代は決算・申告を累計500件以上担当。現在はWebマーケター。