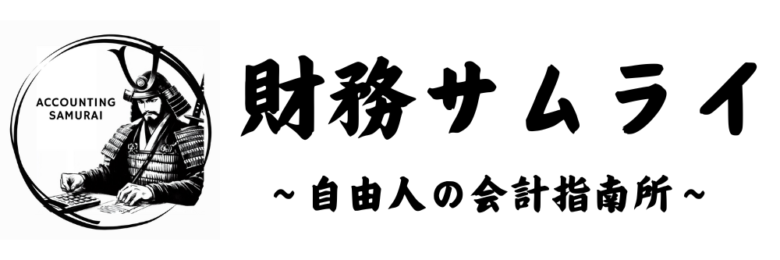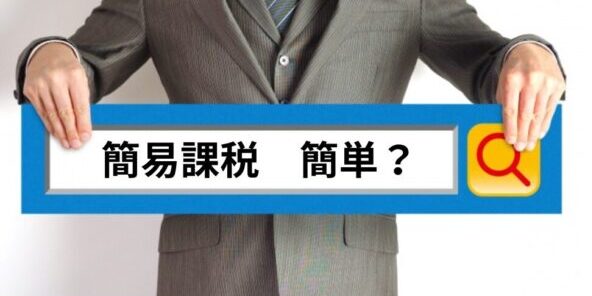
- 「簡易課税は計算が簡単?」
- 「原則課税と簡易課税どっちを選ぶべき?」
- 「簡易課税制度の適用要件や手続き方法は?」
会計処理する上で簡易課税を選択すべきかどうかは気になるところですよね。
本記事では簡易課税制度の内容とメリット&デメリット、選択する際の注意点などをまとめていますので、簡易課税制度の選択を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。
消費税の簡易課税制度

簡易課税制度とは?
簡易課税制度とは、納める消費税を計算する方法の一つです。
消費税を計算する方法は、原則課税と簡易課税の2つの方法があります。
簡易課税制度の概要
簡易課税制度は、消費税の計算を簡略化できる制度です。
特に中小企業や個人事業主にとっては、複雑な仕入税額控除の計算を簡略化し、税務処理の負担を軽減することができます。
原則、納める消費税の計算は売上に対する消費税と仕入れに対する消費税をそれぞれ計算し、その差額を導き出します。
しかし、簡易課税制度を利用すると、売上に対する消費税だけを計算し、仕入れ分の控除は業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて簡単に計算できます。
簡易課税制度を利用することで、消費税の計算が簡単になり、経理作業の負担が軽減されます。
原則課税とは?
消費税の原則課税とは、売上に対する消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて納税額を計算する方法です。
企業は売上時に消費者から消費税を預かり、仕入れ時に支払った消費税を差し引くことで、最終的な納税額を計算します。
例えば、ある店舗が1,000万円の商品を売り、その際に100万円の消費税を受け取ったとします。
一方、その店舗が500万円分の商品を仕入れ、50万円の消費税を支払った場合、最終的に納める消費税は、受け取った100万円から支払った50万円を差し引いた50万円になります。
つまり、原則課税では、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引くことで、実際に負担すべき消費税額を計算します。
簡易課税制度の適用要件
簡易課税制度を利用するための特定の要件を満たす必要があります。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること。
例えば、個人事業主が2024年度に適用する場合、2022年度の売上高が5,000万円以下でなければ適用できません。 - 事前に税務署に届け出をすること。
適用を希望する課税期間開始前に「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
この制度は、消費税の計算を簡略化し、特に中小企業や個人事業主は経理負担を軽減することができます。
簡易課税制度を利用するためには、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることと、事前に選択届出書を提出することが必要です。
基準期間とは?
基準期間とは、消費税の課税売上高などを判断するための特定の期間を指します。
法人の場合は前々事業年度、個人事業主の場合は前々年の1月1日から12月31日までの期間となります。
この期間の売上高が、簡易課税制度を適用するための基準となります。
※基準期間の判断と課税売上高の計算は場合によって複雑なものになるので、専門家に相談されることをおすすめします。
簡易課税制度のメリットとデメリット
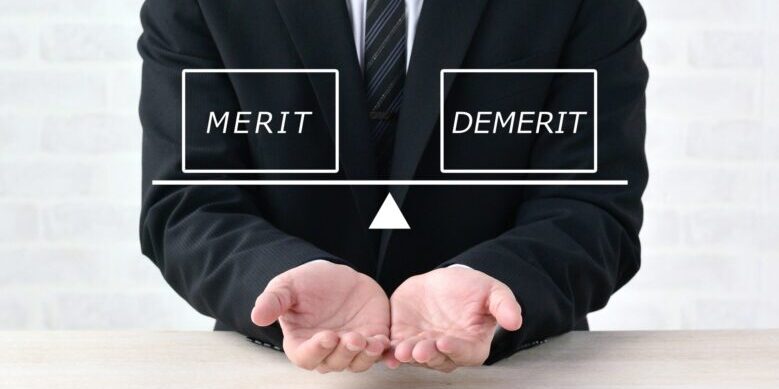
簡易課税制度は中小企業や個人事業主にとって便利な制度ですが、適用条件の確認や納税シミュレーションした上で選択することが推奨されます。
簡易課税のメリット
- 消費税の計算が簡単
- 会計処理が簡素化される
それぞれの項目について解説します。
消費税の計算が簡単
通常、消費税の納税額を計算するには、売上と仕入れの消費税を詳細に計算する必要があります。
しかし、簡易課税制度では、売上高に対する消費税だけを計算し、仕入れにかかる消費税は業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いるため、計算が原則課税と比べて簡単です。
会計処理が簡素化される
消費税の会計処理は、原則課税の場合に課税、非課税、不課税などの区分を、一つ一つの取引ごとに判断して処理します。
例えば、商品の仕入れは課税取引、保険料の支払いは非課税、収入印紙の購入は不課税、といった具合に取引ごとに判断し、会計処理を行う必要があります。
これに対し簡易課税制度では、売上高に対する消費税だけを計算するため、会計処理時の消費税の判断が少なく、処理を簡略化することができます。
簡易課税のデメリット
- 税負担の増加リスク
- 高額な設備投資時の影響
- 会計処理が逆に大変な場合もある?!
それぞれの項目について解説します。
税負担の増加リスク
簡易課税では業種ごとに決まった「みなし仕入率」により消費税額を計算するので、実際の仕入や経費が多い場合、みなし仕入率による計算では、結果的に税負担が増える場合も考えられます。
設備投資時の影響
たとえば、社屋を建設する場合や、事業用トラックを購入する場合など高額な設備投資を行うときに原則課税を利用していれば、多くの仕入税額控除が受けられます。
この場合には納める消費税が少なくなったり、消費税が還付される場合も考えられます。
一方、簡易課税では決まった率で計算した仕入税額控除が適用されるため、場合によって簡易課税は不利になることがあります。
簡易課税を選択するかは、専門家に相談し、十分なシミュレーションを行うことが重要です。
会計処理が逆に大変な場合もある?!
「簡易課税は会計処理が簡略化できる」と先述しましたが、実は逆に難しくなるケースがあります。
簡易課税では業種ごとに決まったみなし仕入率を使うため、業種ごとの売上を区分する必要があります。また、みなし仕入れ率は業種ごとに第1種から第6種まであり、その種類ごとに区分けすることになります。
例えば、個人スーパーのケースでは、近くの飲食店に卸売販売、店の来店客に小売販売、総菜を調理して販売、商品の配達料は別に受け取り、また、駐車場の一部を貸しているなど、このケースでは売上の種類が多いので区分けするのが大変です。
区分け例
- 卸販売・・・第1種
- 小売り・・・第2種
- 総菜・・・第3種
- 配達料・・・第5種
- 駐車場賃貸・・・第6種
簡易課税では上記のような区分けが必要です。
逆に会計処理が難しくなるケースもありえますので、専門家と相談して課税方法を判断すべきです。
簡易課税と原則課税の選択ポイント
ポイント
- 事業の規模や仕入・経費の割合
- 事務処理負担の軽減度
- 事前に納税シミュレーション
簡易課税と原則課税のどちらが有利かを判断するために、上記のポイントが重要です。
したがって、事業の規模や仕入れ・経費の状況、事務負担を考慮して、簡易課税と原則課税のどちらを選ぶか、専門家に相談して決定することが重要です。
>>>税理士に依頼する4つのメリットと3つのデメリット徹底解説!不安を解消して最適な税理士を探す!
簡易課税制度を選択する際の注意点

- 2年間の継続適用あり
- 事前の手続きが必要
それぞれの項目について解説します。
2年間の継続適用
簡易課税制度を選択した場合、原則、2年間継続して簡易課税を適用する必要があります。
例えば、個人事業者が2024年に簡易課税制度を選択した場合、2024年と2025年の2年間は原則として、簡易課税制度を継続して使用しなければなりません。
したがって、簡易課税制度を選択する際には、少なくとも2年間その制度を継続して使用することを、念頭に置いて判断する必要があります。
簡易課税制度の手続き
簡易課税制度を利用するためには、事前に届出書の提出が必要です。
また、基準期間の課税売上高が5000万円以下であることも要件にあることを忘れてはいけません。
簡易課税制度選択届出書の提出方法
提出先と提出期限
簡易課税制度を選択するには、所轄の税務署に「簡易課税制度選択届出書」を提出します。
提出期限は、適用を希望する課税期間の初日の前日までです。
必要書類
簡易課税制度選択届出書には、簡易課税制度を選択する理由や事業の概要などを正確に記載します。
顧問税理士がいる場合は、作成・提出をお願いしたほうが間違いありません。
簡易課税制度不適用届出書の提出方法
簡易課税制度をやめたい場合は、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。
この場合も提出期限は適用をやめたい課税期間の初日の前日までです。
※簡易課税は原則2年継続適用なので注意
提出タイミングとその重要性
手続きを期限内に行わないと、適用が認められない場合があります。
事前にしっかり準備し、提出スケジュールを管理することが重要です。
>>>税理士に依頼する4つのメリットと3つのデメリット徹底解説!不安を解消して最適な税理士を探す!
インボイス制度との関連性
インボイス制度と簡易課税の関連性について解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度は、登録事業者が適格請求書(インボイス)を発行・受領することで、消費税の仕入税額控除を適用できる制度です。
2023年10月以降の消費税の計算に影響がでてきます。
インボイス(適格請求書)とは
インボイス(適格請求書)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な、一定の要件を満たした請求書などのことで、「発行者の氏名または名称および登録番号」や「税抜価格または税込価格、適用税率、消費税額」などが記載されたものをいいます。
インボイス制度が簡易課税制度に与える影響
インボイス制度の施行により、簡易課税制度を利用する事業者には、仕入税額控除に関して特段の影響はありません。
簡易課税制度を利用する事業者は、みなし仕入れ率に基づいて仕入税額を計算するため、仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の取得が必要ではないからです。
例えば、ある小規模な飲食店が簡易課税制度を利用している場合、この飲食店は売上高に対してみなし仕入れ率を適用して仕入税額を計算します。そのため、仕入れ先から適格請求書を受け取らなくても、税額計算には影響がありません。
したがって、簡易課税制度を利用する事業者は、インボイス制度が導入されても仕入税額控除に関しては現在のままの仕組みで対応でき、消費税の計算上は特段の影響はないといえるでしょう。
実務上の対応策
簡易課税制度では、仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の取得が必ずしも必要ではないですが、インボイスの登録事業者となれば、相手先にインボイス(適格請求書)を発行する必要があります。
インボイスを発行するために、レジの設定や導入、請求書等のインボイスへの対応など、対応策を計画し実施することが重要です。
まとめ

消費税の簡易課税制度は、事務負担の軽減や消費税計算の簡便さを提供する一方で、事業の規模や内容に応じた選択が求められます。
この記事では、簡易課税制度の内容、制度のメリット・デメリット、手続きの詳細、選択時の注意点、そしてインボイス制度との関連について解説しました。
簡易課税制度を選択することで、事務作業が軽減される一方、実際の経費金額に基づく控除ができない点がありますので、とくに高額な設備投資を予定している場合には注意が必要です。
また、インボイス制度との関連についても理解を深めることで、より適切な税務処理が可能となります。
事業の特性や将来の展望を踏まえ、どちらの制度が最適かを慎重に検討することが重要です。
税理士などの専門家のアドバイスを受けながら、自社に最適な制度を選択し、効率的な税務管理を実現しましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
執筆者:プレノト
会計事務所時代は法人、個人の申告を累計500件以上担当。現在はWebマーケター。